

 |
中国茶の起源 |
中国茶の発展 |
中国茶の種類 烏龍茶の歴史 | 烏龍茶の品種 近代の中国茶葉輸出の隆盛 | 中国茶葉輸出の衰退 中国茶戦後から現代へ | 日本市場と中国茶 楼蘭と中国茶 |
 |
1 中国茶の起源
茶樹は植物として、7・8千万年の古代から地球上に存在し、中国で茶を栽培し飲用とした歴史は今から三千年以上前からの事とされ、もっとも古くても一万年以上前には遡らないと言われています。

|
| 雲南省西双版納に存在した樹齢800年の栽培茶樹「茶樹王」 |

|

|
| 多くの少数民族が集う雲南省昆明の市 | 色鮮やかな民族衣装 |
茶の木の起源は、インドとする説も有りますが、現在では中国の雲南省或いは四川省とする説が有力で、現在でもそうした地域の山間部には苗族・瑤族・黎族等々多くの少数民族が暮らしています。中国人は今でも黄帝・炎帝の子孫と自称しますが、紀元前のはるか昔に少数民族が中原の地で融合し中華民族を形成し、その過程でお茶を飲む習慣も少数民族から中国人へと伝わり、歴史を経て世界中へと広がっていったと言うことでしょうか。
中国の神話には多くのバリエーションが有りますが、伝説上人物の初代は、家を作ったとされる“有巣氏”、二代目が火を用いることを人々に知らしめた“燧火氏”、三代目は、縄から網を作り漁業を発展させた“伏儀氏”、四代目“神農氏”は農業・医薬の神様とされています。“神農氏”は、狩猟を中心とした時代から、原始農業の時代へと移る転換期を象徴する人物とも云われ、人々にとっての食用・薬用の植物を調べる為、一日に百の草を食べ70の毒にあたり、茶を以って解毒したと伝えられています。中国の神話時代に於けるお茶に関する伝承です。そして五代目は中原伝説の皇帝、黄帝の時代になります。
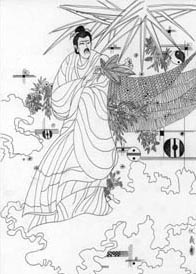 |
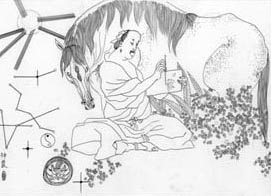 |
| 伏義氏 | 神農氏 |
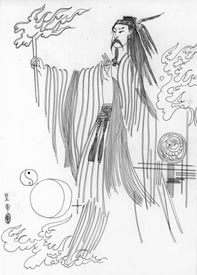 |
黄帝 |
2 中国茶の発展
西漢の時代(紀元前206から紀元8年)以前には、お茶を飲み栽培する習慣が発祥地から長江をつたって湖北・湖南・江蘇省一帯へと伝わったとされています。唐の時代(紀元618年から907年)に茶葉は隆盛期を向かえ、茶を飲む習慣はモンゴル・新彊省・或いは北方の各民族へと広がったとされ陸羽が茶経を記したのもこの時代の事でした。
またこの時代、日本では最澄が茶の種子を持ち帰り、近江の台麗山に植えたと伝えられています。
その後の北宋の時代(960年から1279年)には茶の製法が発展し、続く元(1271年〜1368年)や明(1368年〜1644年)の時代には釜蒸し・釜炒り、コウ青(hongqing)・晒青等々、現代に繋がる多くの製茶法が相次いでに確立しました。この時代に中国茶はその製茶法・品種の多用化により、外見上或いはその品質の上で多種多様なものとなりました。
