
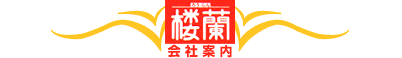
ベールを脱いだ「安渓」(その3)
◇鉄観音のふるさと 中国福建省 日本食糧新聞 昭和61年11月6日号より◇
鉄観音の茶園を訪問
9月30日早朝、泉州から再び安渓に向かう。今日は安渓の街から15キロほど奥に入った茶園の参観とのこと。水量 豊富な西渓という川に沿って安渓の街からさらに北へ遡る。平地には黒い土の畑があるが、上流に向かうにつれて平地は少なくなり、ゆるやかな山地が続く。山の土は異様なほどに赤味を帯びてくる。酸性の強いこの異様な赤土こそ鉄観音の独特の風格の主因であり、この土を離れると鉄観音は鉄観音の味を失うとのこと。平地の黒土には茶の苗床は作るが茶畑は作らないそうで、安渓以外の鉄観音がおいしくない理由の一つはこの赤い酸性土がないためのようだ。
丘をひと登りすると金谷渕港茶菓場という建物の前に出て、そこから緩やかな丘陵の南斜面 に茶畑が広がっている。3年前に新しくつくられた茶園で茶樹はまだ50センチ程であり、切り開かれた畑の赤土を覆うほどには成長していないので、畑の土壌の赤味が異様なほどに強い印象を与える。しかし流石に新設の茶園で、スプリンクラーが随所に設置され、盛んに撒水に活躍していた。本山、毛がに、奇蘭など色種としてブレンドされる各種の茶種と単一品種の鉄観音、黄金桂など、安渓の主力茶種の多くが栽培されている。おそらくこの茶園は新設のモデル茶園で、実験栽培の場なのだろう。ここまでの間にはほとんど茶園を見なかったので安渓の実際の主力茶園はもっと奥地にあるようだ。
腰に竹籠を下げた娘さん達が鉄観音の茶畑で茶摘みをしていた。摘み方は一芯三葉、一本の枝先の三枚目の葉までを、中腰の姿勢で丹念に手摘みしてゆく、茶摘み娘は見た目には風情があるが、実際には大変な労働であり、日本では最早よほどの高級茶でなければ行われていない。烏龍茶がおいしい一つの重要な原因は、三枚目までの葉だけを摘むというこの娘さん達の丹念な手間にかかっていると言って間違いないだろう。

毛茶(荒茶)の手造り
茶園の入口の赤谷渕港茶菓場という建物が毛茶(荒茶)をつくる作業場であり、今はまだ秋茶の季節には少し早いが特別 に実演しておみせしましょうと言う。武夷山など十数回の産地参観を重ねながら、今まで、毛茶の製造は見せてくれたことがあない。カメラ、ビデオもOKという県長の特別 の配慮を得て撮影係は夢中になって飛び回る。毛茶の製造は親戚の間でも見せない秘伝の部分が多くあるそうで、われわれもあまり多くの説明は求めなかった。
ただ一つ、機械揉の後、揉まれた茶葉を布に包み、直径15センチほどの団子にして力をこめて繰返し手揉みする工程だけは、他のどの産地にもない安渓独特の方法であり、この手揉みによって鉄観音のかっちり締った独特の捻れが形づくられる。体重を両手にかけて捻り込む。おそらく数百回に及ぶこの手作業は安渓の茶造りの核心をなす工程であり、安渓烏龍茶は手造りの美術工芸品です、と言う安渓県長の表現が心に沁みて実感できた。驚いたことにこの手揉みは鉄観音だけでなく、色種など安渓の全ての烏龍茶についても行われており、他の産地にない安渓の誇る独特の技術的特徴となっている。

本当の素晴らしさを
つくりたての黄金桂の毛茶を工場長がご馳走してくれた。その素晴らしい香りを楽しみながら、茶の等級のきめ方について質問する。この工場のような毛茶製造の作業所、安渓茶庁のような大きな製茶工場、厦門茶葉支公司のような輸出機関にはそれぞれ「茶師」という専門家がいて、その感覚テストによって等級が決められるが、その各段階の茶師がすべて一級と判定しなければ一級にはなれない。格下げされることもあるのだ。
茶畑の土壌、その年の気候はもとより、茶摘みの日の天気、毛茶づくりの発酵の度合と天候の関係などなど全ての条件が一致して良くなければ一級茶はつくれない。
茶師の多くは福建省茶葉学会に所属する。私の同志であり、その専門家としての技術水準の高さが福建省烏龍茶の品質を守っているのだ。そして最後に厦門など積出港の商品検験局の国家規定の商品検査をパスして初めて正規の国際商品として輸出される。しかし最近この正規のルートによらない闇商品(中国では水貨と呼ぶ)がどのようにかして日本にも多く輸出され、その数量 は福建省茶葉分公司の推測によると正規商品とほぼ等しいほどに達していると言う。
安渓は素晴らしい産地である。県長をはじめ香りと味の芸術に夢をかける多くの人々がいる。私達のために昨日わざわざつくってくれたと言う黄金桂の新茶の香りに酔いながら、この福建省烏龍茶の素晴らしさを日本の人々に伝えることに生涯をかける幸せをしみじみと感じつつ工場に別 れを告げた。
(福建省茶葉学会名誉会員・(株)楼蘭代表・甘利仁朗)

