
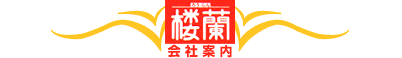
ベールを脱いだ「安渓」(その2)
◇鉄観音のふるさと 中国福建省 日本食糧新聞昭和61年11月6日号より◇
製茶段階を追っていろいろな機械へ
陳県長が先頭になって工場の参観がはじまる。広々とした敷地にいくつもの大きな工場と倉庫が並んでいるが、そのいくつかは新築であり、この茶庁が烏龍茶の国際商品化のスタートと共に近年著しく発展しつつあることがわかる。工場の4階から製茶の段階を追っていろいろな機械が駆使されて毛(まお)茶(日本の荒茶)から次第に形状、品質が整えられてゆく。篩いによる大きさの選別 、風力による重さの選別、さらにくきの除去を経て1階まで下ると、茶は次の棟に運ばれて人の肉眼による最終選別 の段階に入る。
これまでの段階は中国の工場としては、その著しい機械化に驚かされたが、この最終段階は機械を全く使わない完全な肉眼選別 であり、清潔なタイル床の新工場に700人の女子労働者が整然と配列され、黙々と選別 を続けているその人の海に驚かされた。純白の作業衣に純白の帽子の娘さん達が器用な指先で茶を選別 していく。第一の籠には発酵が不十分で緑色の濃すぎるもの、第二の籠には取り残された茎、第三の籠には異物をと、目にも止まらぬ 指先が選び分けていく。自動化できないこの選別工程が、高い品質を保つためにはどうしても必要であり、われわれはこの工程に全従業員の半数以上の人員を投じ続けていくという工場長の説明に、品質にかける頑なな覚悟を強く感じた。

国家金賞に輝く安渓鉄観音特級
鉄観音は安渓が生み安渓が育てた福建省烏龍茶の名品である。清朝の中期に安渓の王土譲という人が大きな岩の上に生えている茶樹から茶をつくったところ大変においしく、病気の母親もその茶を飲んで病気が治った。進士の試験を受けに北京に上った王土譲はその茶を朝廷に献上したが、時の乾隆皇帝がその味をめでて鉄観音の名前を賜った。ほかにも諸説がありますが、これが鉄観音の名前の由来です。と県長さんは説明した。
純粋の安渓鉄観音には「音韻」と呼ばれる独特の風格があると言う。飲んだ後しばらくしてからのど元から甘みが口中にひろがり、爽やかな香気が深遠に持続する。それは正にひとつの芸術です。そう説明する県長は、安渓の茶にほれ込んだ安渓の茶人の代表であった。
安渓鉄観音には特級から4級の5つのグレードがあり、輸出品番としてはK100からK104で表示される。1982年に安渓鉄観音特級は国家金賞を獲得しました、県長はその賞状を胸に抱いて見せてくれる。
その金賞は一度獲得すると、その後毎年厳重な審査があり、それに合格しないと即座に取り上げられてしまうということである。
K100は現在もそれを保持し続けているが、茶の世界では国家金賞は後にも先にもK100のみであり、安渓茶庁の鉄観音特級が烏龍茶だけでなく全中国茶の最高の名品である証明となっている。安渓茶庁の入口正面 にはその栄誉を記念して幅10メートルに及ぶ大きな表彰板が立てられている。
玄関への帰り道に検験室という表示のある室があったので入って見る。きき茶をするための茶器を置く台のほかは壁面 全部に標本棚が並んで200グラムほど入る缶がびっしりと並んでいる。
製茶された全ロットの茶がこの室で厳密に検査され、グレードの最終決定が行われるそうである。その全ロットの見本茶を納めた標本棚は、この茶庁の品質管理の確かさを示すように整然と並んでいた。
昼食は県庁の食堂でご馳走になる。外国人に食事を出すのは初めてとのことで県長はしきりに味つけを気にしている。大変なご馳走で昼食に二時間半かかり、午後の懇談会の時間がなくなってしまったのは残念だった。
安渓には宴会の場所がないとのことで県長以下幹部の皆さんは二時間の道のりを泉州まで同行し、泉州の華僑大厦で歓迎の宴会を催し、夜遅く再び安渓に戻っていった。
(福建省茶葉学会名誉会員・(株)楼蘭代表・甘利仁朗)

