
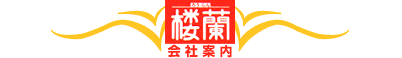
ベールを脱いだ「安渓」(その1)
◇鉄観音のふるさと 中国福建省 日本食糧新聞昭和61年11月6日号より◇
鉄観音のふるさと「安渓」(中国福建省)がようやくそのベールを脱いだ。日本では第一次の烏龍茶ブーム以来、どこか神秘性を秘めたその名前が烏龍茶の代名詞のように伝播し、ひところは鉄観音茶でないものまでが僭称して流通 するという状況さえ生まれた。産地の安渓がこれまで外国人の視察を認めなかったこともかえって名声を高める一因であったかもしれない。その安渓が10月1日から、ようやく外国人に開放された。武夷岩茶に続いて、双璧をなす安渓鉄観音がベールを脱いだのである。記者も10月下旬に、日本人視察団第三陣として鉄観音のふるさとを垣間見ることができた。以下、視察報告を連載するが、第一部は第一陣として安渓を訪れた(株)楼蘭代表・甘利仁朗氏の視察報告を三回にわたって掲載、第二部は記者が武夷岩茶を含めて視察報告をする予定である。
初めての外国人
「鉄観音」の名は烏龍茶の代名詞のように日本では最もよく知られるようになりながら、鉄観音の産地「安渓」を見た日本人はこれまでになかった。それは台湾と向かい合っている福建省の地理的制約のほかにも、道路、宿泊施設などが未開発であるという辺境的制約もあったようだ。
鉄観音と並んで福建省烏龍茶の双璧といわれる武夷岩茶の産地、崇安県へは1980年に外国人として初めて訪れることができたが、安渓県への産地参観はどうしても許可が取れなかった。30回を超える訪中のたびごとに申請を繰返した後、私達はこの9月末にとうとう念願の安渓入りの許可を外国人として初めて得ることができた。
9月28日に泉州に一泊した私達は厦門茶葉支公司三人、泉州対外貿易公司二人の先生方の案内のもとに、翌早朝マイクロバスで安渓に向かった。安渓には外国人の泊まれる宿泊設備がないため、片道二時間の距離を泉州から二日間往復しなければならない。

茶農の独自工夫
南安県を過ぎると道は次第に山合いに入り、舗装もなくなるが思ったよりは悪くない。明後日の国慶節のために谷間の吊り橋が色とりどりの旗で飾られている。家畜の飼料にするのか小山のような枯草を娘達がてんびん棒でかついで行く。安渓県に入ると、ところどころに茶の苗床が見られるようになる。びっしりと密植した茶苗は15〜30センチほどに成長し、その上に日本のすだれのようなもので水平に日覆いをかけてある。
種子による有性繁殖は花粉による雑種交配の危険が大きいので、安渓では昔から挿木による無性繁殖で茶種の純粋性を守っているそうだが、その方法は安渓の茶農達が工夫した独自のもので、清朝初期に安渓が生んだ名茶・鉄観音の純粋種は、茶農たちの営々たる努力によって今に伝えられているのである。
人口80万の安渓県の中心である安渓の街を通り過ぎて5キロ程行くと安渓茶庁の門が見える。門の前に黒山の人だかりがしている。何かあったのかと聞いてみると、あなた方を見るために近くの人達が集まったのだという。私達が安渓を訪れる初めての外国人なのだということを改めて確認する。工場の玄関には安渓県長、工場長をはじめ、昨年、筑波万博や静岡の国立茶業試験場に御招待して、楽しい旅を共にした安渓県の訪日団の4人の方々が、「今度は私達が案内します。」といって揃って出迎えてくれた。
数十人の出迎えの人々にあいさつしながら接待室に迎えられたが、その間地元のカメラのフラッシュを浴びる。30代の若い陳県長が農学校の出身とのことで、茶にくわしく、ふる里安渓の茶を国際商品として世界に発展させたいという強い意欲が感じられた。
10年前に楼蘭が安渓鉄観音を3t初めて日本に輸入し無料で配布したことがきっかけであり、安渓が初めて迎える外国人は楼蘭にしてほしいと福建省に強く要望してきたとの話を聞き、一同大いに感激する。
工場長からは安渓茶庁の説明を受ける。安渓の茶業はおおよそ1000年の歴史を持つが、この工場は30年前に設立され、敷地は4万6400平方メートル、労働者は1400人。茶種は鉄観音、本山、毛ガニ、黄金桂、奇蘭など種類が多いが、輸出用のバラ茶としては純粋種としての鉄観音と各種ブレンドの色種の二種類であり、共に特級から四級までの五段階のグレードがある。
製茶量は2500トンで、うち鉄観音は約10パーセントとのこと。それにしては日本でも香港でも色種という名はほとんど見かけないが、その多くは鉄観音の名で売られているようだ。出された黄金桂のおいしかったこと、こんなお茶を日本で売りたいものである。
(福建省茶葉学会名誉会員・(株)楼蘭代表・甘利仁朗)

