
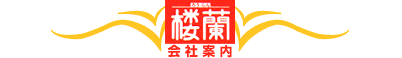
対談 ウーロン茶の神髄を語る(その2)
◇作家 陳 舜 臣氏 楼蘭社社長 甘利仁朗 日経流通新聞昭和55年10月6日号より◇
発酵の止め方に高度な技術
甘利 紅茶は完全発酵茶、ウーロン茶は半発酵茶という違いがあり、その半発酵茶の中にもウーロン茶とプアール茶とがあるんですが、二つの種類の違いを日本の人は時々間違っています。
ウーロン茶は発酵させてから途中でいかに発酵を止めるか。という高度な技術を必要とするので、生産量 もごく限られています。プアール茶は逆に緑茶を作ってから発酵させる、自然発酵のような形のものですから生産量 も多いのですが、ちょっとカビ臭くて漢方薬のようなにおいがするので日本では薬局でよく売られています。製法は逆なんですね。
―ウーロン茶でも産地と、発酵をどこで止めるかという技術が伴わないと、いいお茶は出来ないということですね。
陳 そこにはいろいろな秘けつがあるようです。
甘利 大師という熟練した専門家が国家基準に従って厳密な等級分けをしており、通 常人の五倍程の給料をもらっているということです。
極意をきわめた人たちで、製法、等級分けなど、その人がいなければ始まらないというほどのお茶の名人です。
陳 大師は無形文化財のようなものですね。
甘利 明治のころ、中国茶が欧州に人気を博したので、日本でも製造して輸出しよう福建省から技術者を呼び寄せ、宮崎方面 で作らせたそうですがうまく行かなかったらしいですね。宮崎のお茶は、中国茶に似ているので、最近は人気があるそうですが、ウーロン茶のまぜ物に使われなければよいがと心配です。

嗜好品として飲むのが本筋
―ウーロン茶ブームで輸入量もぐんぐんふえていると思いますが、今年の見通 しは?
甘利 中国茶全体では四月末までに約九百五十トンと昨年一年間の輸入量 を超えています。
―すごい勢いですね、どうも日本国内ではそれを上回っているらしく、最近の新聞報道では混ぜ物の中国茶さわぎも起こっていますね。
甘利 一つの食文化の交流が起ころうとしているのに、ブーム的要素で始まったことを私どもは警戒しています。
せっかくの食文化の交流がエコノミックアニマル的行動によって壊滅してしまうという危険が出ているからです。
お茶の中国側輸出の窓口である中国土産畜産進出口公司も日本市場の混乱を大変心配されており、目に余る場合は注意しているということですが、改まる気配がありません。
現在、中国茶流通ルートは中国から直接入るもの、香港から来るもの、台湾から入るものの三つあります。
中国でパックされた小箱は「中国土産畜産進出口公司」の名入りで直接輸入だから間違いありませんが、それとまったく同じパックが最近若干出回り初めてなかなか区別 できないという事実もあります。
これとは別にバラ積みウーロン茶といって中国語では「散装」と書きますが、これを輸入する代理店は私どもと他一社の二社だけ。そこが輸入して日本で箱詰めしております。
これが中国ルートです。福建省ウーロン茶(散装)について中国は、二社以外には日本向け輸出をしない契約になっていますので、代理店ルート以外はすべて香港ルートになります。香港から来る中にもいろいろあります。
香港茶商の中には、安い台湾茶と混ぜているものもあり、また日本に来てから番茶や九州の釜炒(い)り茶と混ぜられているものもあるようです。
しかし、中には本物もあるようですし、中国土産特産進出口公司でも、どれが本物か区別 がつかず、日本に出回っているものを店先から買い集めて福建省に送って分析しているようですが、結果 がどうでますか…。
台湾からのものの中にもごく少量ですが良いものがあるようです。しかし、一般 に台湾では、緑茶以外を包種茶といっています。それと識別がつきません。混同されて入って来ているようです。横浜の岸壁に着いたものを見ると「包種茶」とあり、カッコして「ウーロン茶」と書かれています。まあ区別 がつかぬ状態で、「ウーロン茶」として売られているものもかなりあるようです。中国本土と異なり、国家基準の検査がないので、どれが良品か識別 するのがとても難しいようです。
―「やせる」とか「健康にいい」などと思ってウーロン茶を飲んでいる人もいるようですが…。
陳 それにも個人差がありますね。同じ薬を飲んでも効く人とあまり合わない人があるように、これもまったく効果 ない人もいると思います。
しかし、ウーロン茶をやせる薬として飲むのはおかしい。薬品ではなく嗜好品ですからね。

これから着実な成長商品に
―「やせるお茶」とかいうのは行き過ぎですね。
陳 僕は医者でないから分析をしていないが、油っこい料理を食べたあとウーロン茶を飲むとスッキリします。脂肪が取れているかどうかわからんが、体験的にいえることは、ウーロン茶を飲むとからだに油をかんじませんね。
甘利 日本の食文化と中国の食文化とは基本的な違いがあるような気がします。
例えば、日本茶を考えると茶道に結びついて礼儀という形に発展しましたが、中国の茶はそういう方向ではなく、食物全体で健康をコントロールするものの一つなんですね。
中国食は非常に合理的に出来ており、野菜のバランスも、油のバランスもうまく取れています。食物に対する考え方の違いといった面 もあります。
それが、日本に入って来ようとしている。違った文化のよさ、食事のよさみたいなものが受け入れられて来ているのではないかと思います。
陳 中国には漢方薬がありますが、食事そのものの中に“薬的”要素も含まれているんです。例えば、お年寄りの誕生日に長寿の縁起でそうめんを食べさせますが、一緒にゼラチン質のものをとって関節を補強するとか、食物自体に健康に役立つものがあります。即効性はないが長い間食べていると効くといったものです。
―取り合わせ、組み合わせがうまく出来ていますね。また中国には食べながら、お茶を飲みながらよく語らう―という風習があるでしょう。
陳 昔から茶館、茶荘というのがあって、年寄りが西瓜(すいか)の種子をかじりながらよく話をする。社交場にもなっています。一家団らん、特に一家プラス近所の人、同族が集まって茶を飲み、食べながら楽しむ風習です。
―人によっては薬のつもり、やせるために飲んでいる人もあるかも知れませんが、飲む程においしいお茶ということがわかって来るでしょう。
陳 すぐにということでなく、経験によってそうなるでしょう。
甘利 正直いってこれからではないでしょうか。今、日本に中国茶と称する銘柄は約百なるのではないですか。それがどうなっているのかわからないのが現状です。
全く混乱状態で、どれがおいしいか、まずいかはデパート、スーパーの担当者でもわかりません。
そんな状態ですから、これから消費者の選別が始まり、正しい形で残ればそれが定着するようになると思います。
中国土産畜産進出公司では来年三月、四月全国五ヵ所のデパートで中国茶展示会を催し、本物のPRをする計画で準備されている。
その段階からほんとうにおいしいお茶が消費者の皆さんにわかっていただけるのではないでしょうか。
陳 先日もある方がいらっしゃって、もうちょっといいのを飲みたいと思っていたが、こんないいお茶があったのか、と言われました。
最後にいいものが勝つわけで、それまでは乱世状態が続くかも知れません。
―味がわかり、味を楽しむ人たちがふえた段階で本当の中国茶人気が出るということですね。
陳 その通りで、今はウォーミングアップという段階でしょう。
甘利 あと五年、十年と八〇年代の成長商品として着実に日本の食卓に定着するとうになると思います。
―十年程前から中国茶を愛飲している一人なので、ぜひそうあってほしいと期待しています。

