
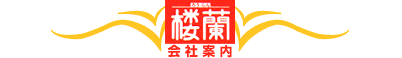
中国の秘境に見た幻の岩茶
◇本懐達成!ウーロン茶のふる里訪問◇
(日本経済新聞 昭和55年6月14日号より)
5年も待った福建省入省
里帰りする海外華僑で満員の中国客船、古浪嶼(コロンス)号に乗船して香港から二十四時間、ポルトガル風の瀟洒(しょうしゃ)なたたずまいを見せる厦門(アモイ)の港の全景に初めて接した時、私たちは感無量 の思いでデッキに立ちつくした。目前に浮かぶ金門島はいまだに台湾領土。中国はこれまで、おそらく国防上の理由から、容易なことでは福建省への入省を認めなかった。ウーロン茶に魅せられてこの五年間、何度断られても申請を繰り返した結果 がついにこのほど実現するのである。
私たちのグループの名は、日本・ウーロン茶福建省訪問団。福建を父祖の地とする作家、陳舜臣氏を顧問に迎え、そのご一家四人を含むウーロン茶に魅せられた「楼蘭クラブ」九人のメンバーである。いまやウーロン茶は日本の食卓に急速に定着しようとしているが、私たちはこの五年間、バカではないかといわれながら広州公益会にそのためだけに通い続けてきたのだった。
上陸の翌日から、中国土産畜産進出公司の十人の人たちが私たちの世話役となった。起居をすべて共にして、昼は見学、夜は意見交換と、日中一体の半月に及ぶ共同生活がはじまったのである。
この時期の厦門は暑からず寒からず、さわやかな海風が街角を通り抜けてまことに気持ちがいい。しかも外国人の人影を全く見ない、別天地のような落ち着いた港町であった。港の沖には、かつて陳舜臣氏が「旋風に告げよ」で小説化された国姓爺合戦の鄭成功の本拠地、古浪嶼島が浮かび、日本生まれの混血の風雲児がオランダから台湾を解放したその記念館は、盛んであった日中交流の歴史を如実に語っていた。さらに校庭に海水浴場をもつ厦門大学の広大なキャンパス。十八皿目以上はどうにも食べられなかった南普陀(ナンプダ)寺の超豪華な精進料理。春の厦門はまさに桃源郷というにふさわしかった。
夕食がすむと、いつも意見交換の時間となった。私たちはまず、通過してきた香港の市場で、日本からの買い集めのため、ウーロン茶の価格がこの半年間で異常に高騰していた事実を報告。これに対して中国側からは、香港の一部茶商は安い台湾茶とミックスして日本に売っているようなので日本の市場の混乱が心配なこと、しかし日本の消費者はやがては良いものと悪いものを必ず選別 してくれるであろうから、あなたたとは福建ウーロン茶の日本代理店として、ウーロン茶の正しい普及のために努力してほしいなどを強く要望された。
さて、私たちの最大の目的は、名茶のふるさと、武夷(ぶい)山脈の山中に入ることであった。まず厦門から泉州へ二時間。かつて「西のバグダッド、東の泉州」とうたわれた世界最大の貿易港も、今はただ静かな漁港である。それから五時間、幹線道路に信号が一つもないのに驚きながら福州へ。滞在すること数日で関係筋へのあいさつをすませた私たちは、そこからいよいよ北の山道に入った。江西省との省境。武夷山脈の奥深く、ウーロン茶の秘境をめざしたのである。

日本茶と違い発酵させる
山道を車に揺られ揺られ七時間、建甌(ケンオウ)に着き、さっそく製茶工場を見学。―福建ウーロン茶は大きく分けて三つの茶種にわかれる。福建省の中央を流れるみん江(ミンコウ;Mingjiang)を境としてみん南(ミンナン;Mingnan)地方には鉄観音(テッカンノン)と色種(シキシュ)、みん北地方(ミンホク;Mingbei)には水仙の三種である。そしてこの建甌は、みん北水仙の中心地であった。
「烏竜(ウーロン)茶」の名は、日本茶と異なり、発酵という過程を経て「色は鳥のように黒く、形は竜のように雄大にくねっている」ところから付けられたものだ。工場では、その大切な発酵の程度をみる色の選別 がたんねんに行われていた。茶葉の色を肉眼で識別し、一枚一枚を手で選り分けるのである。30%の発酵が理想的とのことであったが、余りに厳重な選別 ぶりに私たちはただ顔を見合わせて驚くばかりであった。
翌日さらに車は北上、いよいよ山深くなる砂利道を五時間、ようやくにして武夷山脈の懐深く抱かれた崇安の村に到着した。ここは古来有名な武夷岩茶の名産地で、武夷の山並みに囲まれた高原の一角にあり、空気はよく澄んで空は青く、古い時代の軽井沢を思わせる素朴な美しい村であった。
茶の奥深さ思い知る
長い伝統を持つこの地の茶業試験所は、私たちのために数種のウーロン茶を飲み分ける「きき茶」の会を催してくれた。茶器、湯温を同一に設定し、数種のお茶をいれて心気を統一し、まず香りだけを静かに味わい、それから少しずつ口に含んで茶味を比べるのである。
「武夷水仙」は最初口に含んだ時は上品すぎて味覚に対する刺激が小さいけれど、飲み終えてから少したつと口の中よりもむしろのどの奥でふくよかな甘みを感じはじめ、それが長く持続して何ともいえない豊かな余韻を残してくれた。他方「鉄観音」は、一口含んだだけで清らかな香りと芳潤な茶味が口一杯に広がり、お茶を知らない人でも一口でとりこにされるような、現代的な風味であった。いずれにせよ両者とも私たち“茶キチ”には、お茶というものの底知れない奥深さを感じさせるに十分であった。
岩壁に仰ぎ見る名木
武夷の山深く、「大紅袍」と呼ばれる天下第一の岩茶の名木があることは古くから知られている。しかしそれはあまりにも人里遠く。中国人でもその木を見た人は少なく、まして外国人として訪ねるのは私たちが初めてだということだった。
大王峰や玉女峰、奇岩怪峰を連ねる渓谷に沿って、竹ざおをつえにあえぎあえぎ登った。途中岩茶を栽培する一軒の農家の傍らを通 ったが、何とこの家は二百メートルもある大きな滝の、流れ落ちる水の裏側の岩はだにへばりついて建てられていた。まるで孫悟空の水簾洞のよう。落下する滝の下を駆け抜けて家の中に入ったが、このように人間離れした環境にこそ岩茶は名木として育つのだなあと、感慨ひとしおであった。
峡谷の急峻(きゅうしゅん)な両岸には石垣が階段状に積み上げられ、その上にわずか数本ずつ、武夷の岩茶は植えられていた。登ること数時間。私たちの前に「大紅袍」と赤く刻みこまれた大岩壁が現れた。その垂直の岩壁の途中の岩だなに石垣を積み、畳一枚ほどの石くずの上に、天下第一といわれる岩茶の名木「大紅袍」が仰ぎ見られたのである。ただ一本の正木をはさんで副木が三本。高さ一メートルほどの四本の名木が狭い岩だけに寄り添うようにしてあった。皇帝献上茶として古来有名なこの名木は、石垣を紅の布で覆っていたのでこの名があるが、厳しい自然のみが生み出す武夷岩茶の象徴として、茶の神髄を現代に伝えて硬い岩はだに根づいていたのである。
さて、話はさかのぼるが、私が初めてウーロン茶の魅力にとりつかれたのは五年前のことであった。繊維関係の仕事で中国の広州公易会に赴いた折に、当地でご馳走になったのである。飲んでみて、ともかく素晴らしいと思った。もちろん当時は、日本では全くといっていいほど味わう機会がないものであった。
大変おいしく、素晴らしいと思ったが、同時に私は疑問も持った。「こんなにおいしく思うのは、私だけではないだろうか。この魅力は果 たして、普遍的なものであろうか」―という疑問である。
同行の仲間に飲んでもらい、それぞれ好評であったが、それだけでは安心できない。帰国後、いろいろ考えたすえ、このたびご同行願った陳舜臣氏を訪れて正直に私の疑問をぶつけたのであった。
先生は一冊の本を示された。それは1839年、つまりアヘン戦争が起こる直前までの中国茶のヨーロッパへの輸出について詳細に記してある書であった。一読して私は大変驚いた。中後茶の英国への輸出量 は年間、人口一人当たり900グラムとあるのである。とてつもない数字である。というのも、これはお茶好きの日本人がのむ量 とほぼ同じなのである。驚いたとともに、「果たして普遍性があるか」という私の疑念もいっぺんに氷解したのだった。
しかしこの膨大な輸出も、不幸なアヘン戦争で消えてしまった。困った東インド会社は、中国茶の販売を紅茶一本にしぼって栽培を促進、かくて英国人の紅茶好きが始まったわけである。
こうした歴史をふまえて、中国がいま、ウーロン茶を再び国際市場に送り出そうという意欲は満々のようである。私たち一行も、今回の旅を通 じて改めて「ウーロン茶を世界の飲料に」という夢をふくらませたのだった。

