
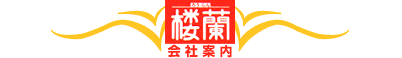
「茶之路」を訪ねて秘められた名茶を探る
昭和62年7月25日 日本食糧新聞
陳舜臣先生と共に
11年前のことでした。当時、中国茶のおいしさに気づきながらその輸入に踏み切れずに迷っていた私にとって、陳先生からお借りした一冊の古書は正に神の啓示でした。それは19世紀の広州に駐在した欧米の貿易業者たちの会報でしたが、そこに載っている烏龍茶を中心とするぼう大な中国茶の輸出統計は、貿易摩擦から阿片戦争を惹起した近代史の重要な転換期の背景を如実に示していました。
それを契機に、烏龍茶の日本初輸入に踏み切って茶貿易の道に入った私達は、1980年陳先生を顧問に組織して福建省に入り、産地の生の情報を初めて日本に伝えることが出来ました。それから十年、いろいろなことがありましたが、烏龍茶は今や緑茶、紅茶に次ぐ第三のお茶として日本の食卓に確実に定着するようになりました。
その先生の奥様から、朝日新聞にお茶の歴史について連載することになったので取材に行きませんかとお誘いがあったのは昨年のことでした。以前「録外録」を執筆されたところにほぼ半年間にわたって「茶之路」を連載されるとのことで、絲綢之路(シルクロード)を歩き尽くされた先生が今度は茶之路(ティーロード)を探るというお話した私達は小躍りして同行をお願いしました。厦門(アモイ)大学に留学中の私の長男を含めて一行五人が北京に集ったのは今年4月1日のことでした。
中国茶業の元老・呉覚農先生
私の所属する福建省茶葉学会から事前にご連絡をとり、中国茶葉学会名誉理事長の呉覚農先生にお会い出来たのは北京東安門の中国茶葉進出口公司の応接室でした。今年90歳を迎える呉先生の誕生日を記念して、数日後には中国茶葉学会の総会が北京で開かれるとのことで、私達からは記念に日本人形をお贈りし、呉先生からは記念出版の「呉覚農選集」をいただきました。
先生は浙江省のご出身だそうですが、旧名の栄堂を自ら覚農と改名されたことからも、農業覚醒に一生を投じた農業、茶業界の元老です。
23歳から3年間、静岡県の国立茶業試験所に留学され、帰国後は中国茶樹原産地考など多くの論文を発表、1920年代には上海の自宅を農学会の事務所に提供して困難な時代の学会を支え、日中戦争中にも、復旦大学農学院に中国初の茶業専修科を発足させ、重慶に中国茶葉総公司を設立するなど、意欲を燃し続けられて、1949年新中国成立と共に中国農学会副理事長、中国茶葉公司総経理に就任。そして現在は中国茶葉学会名誉理事長として、かくしゃくたる活躍を続けておられます。
仲介の労を取っていただいた中国茶葉総公司の王先生からは、ご高齢なので一時間ほどと言われていたのに、呉先生は、雲南の少数民族の間に始まった茶が、四川省で茶園として経営されるようになり、やがて揚子江を下って江南へ達した「茶之路」について延々ニ時間にわたって熱心に説かれたのでした。
近代になってからは、福建省が生んだ烏龍茶、特に武夷岩茶がブラック・ティーと呼ばれ欧米人の間に大変な好評を博したというお話をきき、紅茶の源がやはり烏龍茶であったことを確認できたことは大きな収穫でした。そうでした。烏龍茶の「烏」は中国語では黒を意味する言葉です。
私達がこれから四川、雲南を訪ねますと言うと、呉先生は、「それは大変良い。茶の源流ですから。そして次にはぜひ、浙江省の杭州にも行って下さい」と薦められました。杭州には、お茶好きの人の組織である「茶人之家」の本拠があり、中国茶葉学会の本部もあって、現在では中国茶業の中心となっているそうです。
常務委員として政治協商会議に出席される呉先生とお別れした私達は、翌朝、西安へ、更に五日後成都へと飛びました。
究極の茶「一芯一葉茶」
四川大学には北大出身の高橋耕一郎君が茶の歴史をテーマに留学中で、同君の案内で四川省茶葉分公司を訪問し、陳舜臣先生は四川省茶葉学会の会員に「茶馬交易」の歴史について熱心に取材をされました。
遊牧のチベット族にとって必需品となった四川省の団茶は、彼らとの物々交換の重要な交易品となり、各地に茶馬交易の市が立ったそうで、茶にとってはじめての国際貿易商品であったようです。成都から北と南の方向に青海省、西蔵省に向って延びる交易路があり、その路筋によって団茶は北路辺鎖茶、南路辺鎖茶と呼ばれたそうです。馬一頭につき何キロのお茶と交換されたかたずねると、ほぼ60キロとのこと。茶は当時、大変に高価な商品であったことが判ります。
その茶葉公司で振舞われた新茶のあまりの素晴らしさに公司の経理にたずねると、春一番摘みの一芯一葉茶ですと、答えました。その類い稀な爽やかな香りと、名刀を思わせる、甘えのない切れ上った茶味に、私達は正に茶の真髄を知る思いに打たれました。日本では、考えられない一芯一葉という手づくりの極致が、茶の源流と言えるこの四川省に生き続けていたのです。
少数民族の木登り茶
雲南省の昆明からプロペラ機で一時間、更に野生の象が住むうっそうたる照葉樹林のジャングルを四時間程走ると、ラオスとの国境に近い西双版納(シーサンパンナ)泰(タイ)族自治州の中心、景洪(ケイコウ)に着きます。
翌日は南糯山(ナンノーサン)の中腹でジープを降り、焼畑農法の名残りを思わせる古老樹の散在する急傾斜の茶畑につけられた階段をひたすら下ります。このあたりの茶樹は4〜5メートルに及ぶものが多く、少数民族の女性が茶の樹の上を枝から枝へと渡りながら茶を摘む姿はまるで忍者のようです。千段近い石段を下り切った窪地に、茶之路をさかのぼるこの旅の最終目標、「茶樹王」はありました。樹齢八百年、直径1メートルに近いこの茶樹が日本で言えば平安末期の頃からこの地の少数民族と共に生きてきた永い時の流れを想うと深い感慨を禁じ得ません。

この地の少数民族の焼畑から生まれたお茶が、中国全土へ、印度へと伝えられていった気の遠くなるような長い時間と道筋の出来事を、いま陳舜臣先生は「茶之路」として日本に伝えようとされています。そしてこの道筋には数千年の時の流れに摩かれて茶の真髄を伝える素晴らしいお茶が、まだ日本に伝えられることなく眠っているようです。茶之路に生き残っている名茶を掘り起してみたい。ひそかな夢をふくらませながら、雲流れる雲南の茶畑を、私は陳先生の後について汗をふきふき、息を切らせて登り返して行きました。


